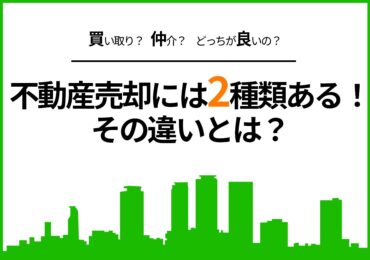相続における遺留分侵害額請求とは?民法改正による違いや手続き方法を解説
2024.07.02

Contents
相続を受ける場合、本来なら分配される分を請求したいと考えることもあるのではないでしょうか。
この記事では、遺留分についての知識や、遺留分が侵害されたと知った場合の請求方法について解説をしています。
また、請求の際に注意すべき点や、民法改正後の内容の違いについても解説しますので、相続を受ける際には参考にしてみてください。
相続遺留分侵害額請求の権利がある方とは

親族や家族が亡くなり、法定相続人の対象となっても、生前贈与や遺言書の内容によっては、本来なら受け取れるはずの遺産をもらえないこともあります。
その場合に、本来もらえるはずの取り分を請求できる、遺留分侵害額の請求についても知っておきましょう。
遺留分とは
遺留分とは、故人の財産を相続する方が受け取れる、最低でも取得できる法律で補償されている割合を指します。
故人の遺言書や生前贈与に関わらず、遺留分は守られるべきもので、侵害されません。
遺留分は、亡くなった方との関係や相続人の人数などによっても計算方法が異なります。
法定相続分の半分が基本の考え方で、故人の配偶者と子ども1人が受け継ぐ場合は、どちらも25%が遺留分です。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、本来受け取る遺産にあたる金額を請求できる、遺産を受け継ぐ家族や親族に認められている権利です。
たとえば、生前贈与や、遺言書の指定によって、特定の親族や、第三者のみが財産を受け取り、他の親族に遺留分が残らなかった場合は、遺留分の侵害にあたります。
贈与や相続を多く受けた方に対して、本来の受け取れる財産の請求が可能です。
遺留分侵害額請求ができる方
遺留分の侵害額請求ができる方は、配偶者の他には、子どもや孫、親や祖父母などの直系の親族です。
兄弟姉妹、甥姪、叔父叔母などは、遺留分が認められず、遺留分の請求はできません。
相続の際の遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い

民法の改正によって、2019年7月1日以降、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請と呼び方が変わりました。
請求権の呼び方以外にも、内容も変更となっています。
改正によって変わった具体的な内容や違いについて、見ていきましょう。
従来の遺留分減殺請求の特徴
2019年7月以前の遺留分減殺請求は、故人の財産を受け継ぐ場合に、遺留分を侵害された財産に対する返還を請求できる権利です。
受け継ぐ財産は金銭だけとは限らず、土地や建物といった不動産の場合も少なくありません。
遺留分減殺請求では、物理的に平等に分けられない遺産の場合には、原則として相続人同士で共有するように決められていました。
不動産の場合は、侵害した方に対し移転登記の請求をおこなえますが、遺留分は現金では受け取れません。
さらに、権利者が複数になると、不動産の売却が煩雑になる、登記の変更や解消でトラブルが発生する可能性もあります。
それが改正によって手続きが簡素化できるようになり、迅速に進められるようになりました。
また、遺産を分配する場合や、遺言書による不公平の解消につながります。
改正後の内容変更
改正前は、原則として、故人の遺産を受け継ぐ場合、遺留分の請求は、現物返還が基本でした。
それが改正によって手続きが簡素化できるため、迅速に分配を進められるようになりました。
遺留分を侵害された場合には、遺留分に相当する金銭を請求できます。
たとえば、遺言書に特定の方のみに不動産をすべて譲ると記載されていた場合、他の親族は、本来受け取れるはずの遺産をもらえません。
この場合、不動産を譲られた相続人に対して、他の相続人は遺留分相当の金銭の要求ができます。
譲られた方は、請求を受けたら精算をして金銭を渡すため、不動産の共有持分を減らす必要がなくなりました。
相続した不動産の売却を検討する際には、スムーズな手続きが可能です。
相続人の間の不公平も避けられる上、特定の方に不動産を譲りたい故人の遺志も尊重されます。
生前贈与の期限
民法改正では、生前贈与で遺留分が侵害された場合の請求権にも変更がありました。
改正前は期限が設定されていませんでしたが、改正では相続が始まる前の10年間の生前贈与に限定され、それ以上前におこなわれた贈与は遡れません。
相続の際の遺留分侵害額請求の方法について

遺留分が侵害された場合、必要となる手続き方法や、期限について知っておきましょう。
遺留分の侵害が分かった場合
遺留分侵害額請求には、時効が決められています。
請求を行使できる時効は、相続が開始されたことと、本来受け取れるはずの遺留分が侵害されたと知ってから1年以内です。
1年を過ぎると権利が失われるため、後から遺留分の侵害請求をしても、認められません。
2つの事実が分かった時点で時効が開始されるため、どちらか1つの事実が分かった時点では、時効は開始されません。
話し合いをおこなう
相続は、ほとんどが家族や親族の間で起こる問題であるため、円満に解決するためには、話し合うことが大切です。
話し合いの場を設けて、遺産の分配方法に合意が得られたら、合意した内容は必ず書面として残しておきましょう。
書面に残さず口頭だけで合意すると、証拠がなくなるため、後々になっていったいわないの水掛け論となり、トラブルに発展するおそれがあります。
合意文書には決まった書式はありませんが、話し合いの内容をまとめた記載の他にも、話し合いに参加した方の署名や捺印を残しておきましょう。
文書は公証役場で公正証書にすると、公証人が作成する公的な文書として証明できますので、トラブルに備えられます。
文書に残したら精算をおこない、自分の遺留分を受け取ります。
内容証明郵便を送付
話し合いで合意が得られなかった場合や、話し合いができない場合には、内容証明郵便を送付して、遺留分侵害額請求をします。
時効が近い場合は、話し合いの途中であっても、内容証明郵便を送付すると、時効が猶予されます。
内容証明郵便とは、記載されている内容を郵便局が確認して、証明するサービスです。
請求権を行使する意思の他に被相続人との関係や財産の内容、遺留分の金額や侵害分の特定などを明記して作成しましょう。
同じ内容の記載を3部作成する必要があり、1部は自分が受け取ります。
内容証明郵便を利用すれば、相手が受け取っていない、内容を知らないといった否定ができません。
郵送した日付も明確になるため、時効の期限の間に請求権を行使できます。
内容証明郵便は、郵便局の他、インターネット上でも利用可能です。
書式や文字数など決まりがありますので、事前に調べて作成をおこないましょう。
請求調停をおこなう
交渉がまとまらない場合には、裁判所に対して、請求調停の申し立てが可能です。
申し立てののち、家庭裁判所で調停がおこなわれます。
調停では、調停委員が双方の主張を聞いたうえで、交渉の仲立ちをおこない、調停案を提案します。
双方が調停案に合意すれば、調停が成立して終了です。
調停が不成立に終わった場合には、裁判所に対して請求訴訟を起こす手続きもあります。
まとめ
家族や親族が亡くなり本来受け取れるはずの遺産がもらえず、遺留分が侵害されていると分かったら、遺留分侵害額請求が行使できます。
遺留分侵害額請求は、財産を受け継ぐ方の権利のため、遺留分相当は請求によって金銭での精算が可能です。
請求の行使には時効がありますので、期限に注意しながら親族や家族の間で、納得いく解決を目指しましょう。